解答:(ア)
解説:
大阪では「半助」とはうなぎの頭のことを言いますな。一説では、かつて「一円」のことを「円助」と呼んでいたそうや。うなぎの頭はざる一杯50銭で売っていたので一円の半分ということで「半助」と呼ばれるようになったとのことや。また、「うずら」は「うなぎのツラ」が短くなったものと考えられます。
他地域ではうなぎの頭は食べませんか?大阪でも段々と食べなくなってきてますかね。ま、食材を無駄なく使います。食材に限らず無駄のないようにという大阪のもったいない精神につながりますかね。決して、ケチ臭いということではありません。
私が子供の頃は、半助は色んな形で食卓にでてきてたかな。庶民の味です。しかし、バブル期以降、もったいないという観念がだいぶ薄れてきて、半助もあんまり食べんようになってきた。しかし、何かを食すというとき、大前提というか礼儀になるのは「丸ごと」ですから、半助も食べましょう😀
で、半助豆腐とは、 焼き豆腐を長方形に切ります。だし汁を土鍋に入れ、焼き豆腐と調味料を入れ火にかける。 沸騰してきたら半助を入れて、最後に葉ねぎですわ。調味料は出汁、砂糖、しょうゆ、酒でございます。これがうまいんですわ。そういや~、千日前に昔、うなぎ屋あって、店先で半助落としとったな~。
そうそう、タイトルの「半助いてまう」はかつての大阪の男衆がけんかするときによく使った表現です。「あたまどつく」ということですが😅
大阪弁クイズ Part 2 半助いてまうぞ! ー食文化ー
 大阪弁クイズ Part 2
大阪弁クイズ Part 2 12
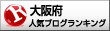

コメント