解答:(ウ)
解説:
これらはすべて大阪府箕面(みのお)市にある地名です。箕面には、地元の人でも最初は読みづらい地名が多いんです。
-
粟生外院(あおげいん):「粟生(あお)」は「粟(あわ)」が多く実った土地を意味します。「外院(げいん)」は仏教用語で、寺の境内の外側の区域を指します。つまり、「寺の外の集落」といった意味をもつ地名やと考えられています。
-
半町(はんじょ):普通は「はんまち」や「はんちょう」と読みたくなりますが、箕面では「はんじょ」。江戸時代の村名がそのまま残ったもので、「繁盛(はんじょう)」に通じる縁起のええ読み方でもあります。現在の半町は旧・箕面村と隣の村の“中間”に位置していました。つまり「町の半分=境目の町」という意味で“半町”と呼ばれたと思われます。
その読みが「はんじょ」となり、いつしか「繁盛」と同音のめでたい地名として定着したわけです。 -
坊島(ぼうしま):「坊」は僧侶の住まいや寺の一部を指す言葉、「島」は小高い地形や他と区切られた土地を意味します。昔は寺院や修行の場と関わりのあった地域やったと見られます。
箕面の地名は、古代の地形・信仰・村の歴史がぎゅっと詰まった“生きた文化資料”や。読み方だけやなく、地名の由来をたどるとその土地の物語が見えてくる。それが地名のおもろいところですわ。

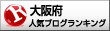

コメント