解答:(ア)
解説:
「空ボケ(そらぼけ)」という表現には、大阪人の“間(ま)”の感覚がよう出ています。
まず語源的に見ると、「空(そら)」には「実がない」「中身がない」という意味があり、「空返事」「空約束」などと同じく、“うわべだけ・本心でない”というニュアンスを含みます。そこに「ボケ(惚け)」がくっつくと、つまり「中身のないボケ」「本気でないとぼけ方」という意味合いになるわけです。
この「空ボケ」、漫才や落語の世界でも古くから使われてきました。
たとえば、相方のボケに対して「お前、それ空ボケやないか!」とツッコむのは定番の流れ。観客に「この人、ほんまは分かっとるのにわざとボケとるな」と感じさせる、その“計算されたボケ”を指すんです。つまり、「天然ボケ」が無意識の笑いなのに対し、「空ボケ」は意識的に場を和ませるためのボケ。ここに、大阪の笑いの奥深さがあるわけです。
この会話の父親も、怒ってるようでどこか笑いを含んでます。
「このガキ、空ボケしとる」──これは「ほんまに知らんわけないやろ」「わざとらしいのう」という、ツッコミと情けの中間のような言葉なんです。
大阪弁には、怒りの中にも笑いと愛情がある。まさに人情の言葉ですな。
ちなみに、「空ボケ」は江戸時代の上方(大阪・京都)でまず文献に登場します。
古くは「空惚け(そらとぼけ)」という形で、「しらばっくれる」「知らないふりをする」という意味で使われていました。
「空」は“うわのそら”“空返事”などと同じく「うつろ」「本気でない」の意。
「惚け」は「ぼんやりする」「とぼける」。
つまり「空惚け」は“うわのそらのようにとぼける”=「しらばっくれる」こと。
江戸にも伝わりましたが、江戸ではあまり日常語として定着せず、
一方の上方(特に大阪)では漫才や落語を通して口語に残ったんですね。
現代でも「空ボケ」は大阪・関西圏では比較的通じます。
ただし、使う頻度は高くなく、年配層や芸人言葉にやや残っている感じです。
芸人でも最近は使わないですね。
「空ボケ」は、“笑いを交えた軽い皮肉”を含むのが大阪的特徴です。
怒りながらも、どこかツッコミのトーンになる——そこが大阪弁らしい味ですね。
東京では「しらばっくれる」「とぼける」、名古屋では「とぼける」「すっとぼける」、
大阪では「空ボケする」「しらばる(しらんふりする)」
という感じで、「空ボケ」は関西文化圏で生き残った言葉ですかね。何度も言いますが、近年では
使う人も少ないかと。
大阪弁クイズ Part 2 ボケてる ーフレーズー
 大阪弁クイズ Part 2
大阪弁クイズ Part 2 12
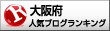

コメント