解答:(イ)
解説:
お好み焼きのルーツには諸説あるが、その一つとしてよく語られるのが「千利休考案説」や。千利休(1522~1591)は堺出身の茶人で、茶の湯の精神を大成させた人物。豊臣秀吉の秘書的な役割も果たしてた。彼が茶席でふるまったとされる「麩の焼き」という菓子が、のちにお好み焼きの原型の一つになったと言われてる。
ただし、これには「ほんまかいな?」という疑問もつきまとう。大正時代には「一銭洋食」と呼ばれる庶民のおやつがあり、それもまたお好み焼きの源流とされてる。今でも、一銭洋食焼きを提供するお店があるよ。また、東京にはもんじゃ焼き、広島には広島焼きといった独自の小麦粉文化があり、「小麦粉を水で溶いて焼く料理」というスタイルは全国各地で自然に生まれていた可能性が高いのかのう。私の聞いたところでは、お好み焼の源流は東京で生まれたそうや。これもほんまかどうかわからんけど。
大阪では、いろんな具材を混ぜ合わせて一枚に焼き上げる「混ぜ焼き」が主流で、これが「お好み焼き」として全国に広まりました。もともとは大阪でも広島風にクレープみたいに焼いてたようや。しかし、かつて大阪は経済の中心。たくさん人がお好み焼屋にやってくる。「もう、全部混ぜて、お客さんに焼いてもらえ。」というのが混ぜ焼の発祥やと聞いてます。利休の時代に始まったかどうかはさておき、堺出身の千利休の名前を出すと、大阪人としては「せやせや、大阪発祥や!」とまとめたくなるわな😀
大阪弁クイズ Part 2 粉もんの話 ー食文化ー
 大阪弁クイズ Part 2
大阪弁クイズ Part 2 12
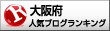

コメント