解答:(イ)
解説:
「みーする」がテーマですな。令和の時代には使われない言葉になりましたな。大阪弁の「みーする」は、標準語にすると 魚の「身をほぐす」とか「骨から身を外す」 という意味ですな。特に サンマやアジなど、細長くて骨が多い魚 でよく使われる表現です。お箸で骨から身をきれいに外して食べやすくする動作を指します。最も私が子供ころでも、あまり「みーする」という言葉は使ってなかったような気がするな。やっぱ、「ほぐす」やったかな。せやから、「みーする」いう言葉はだいぶんとレトロ感のある言葉かな。でも、ええ響きやろ。
大阪や関西だけでなく、広く西日本で「みーする」という言い方は見られるようや。
魚をきれいに食べられるかどうかは昔から「しつけ」の一つとされており、子供が魚の骨を苦手とする場面で、大人が「みーして」食べやすくしてあげる光景は日常的やったはずや。とくにばあさんの役目かな。
大阪弁では「身をほぐす」を短く「みーする」と言うことで、会話がよりテンポよくなってます。
大阪弁クイズ Part 2 みー入ったとはちやうな ー食文化ー
 大阪弁クイズ Part 2
大阪弁クイズ Part 2 12
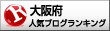

コメント